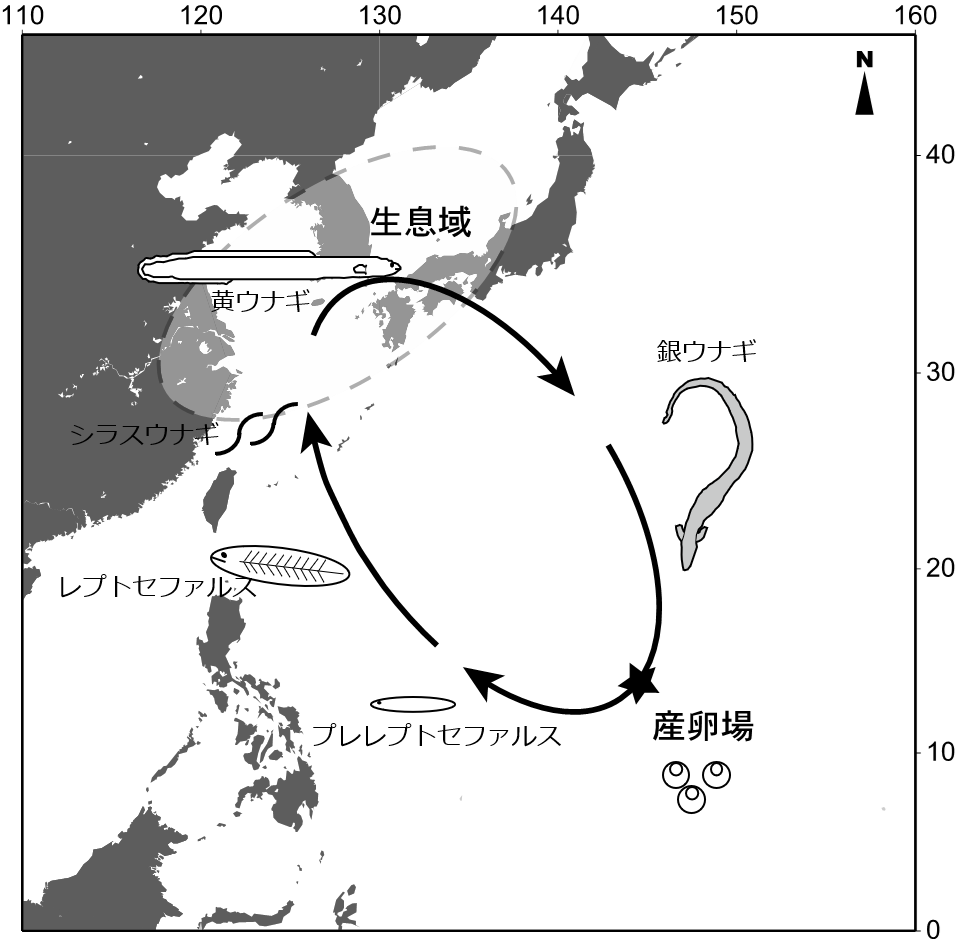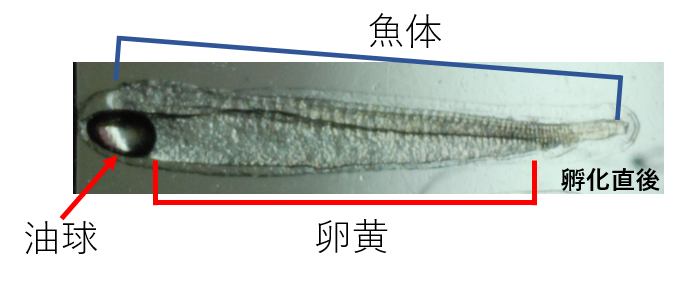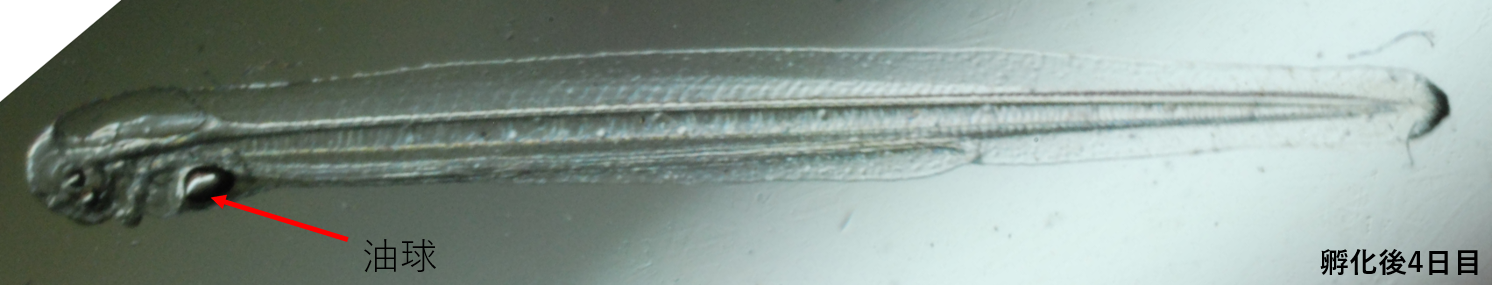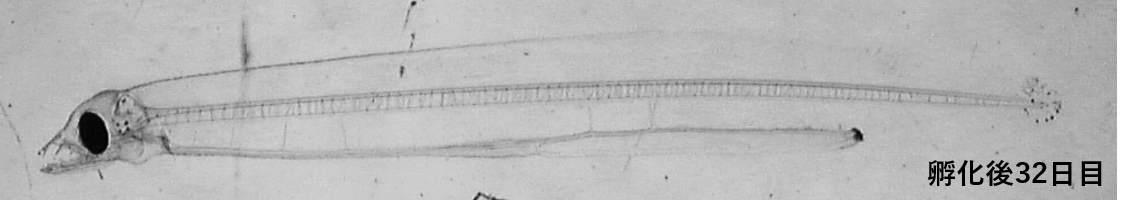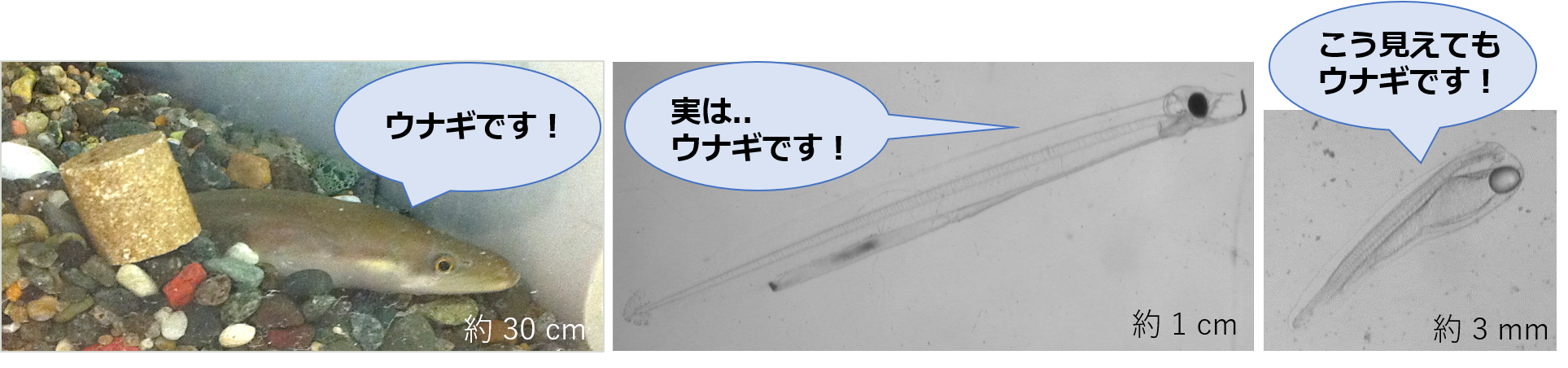ウナギの生活史
セクションアウトライン
-
-
出版社(東海大学出版部)のご承諾のうえ使用しています
-
-
ウナギの生態だけでなく、我々の生活の中でのウナギを幅広く紹介した本です。
-
私の一押し!
分かりやすいクイズ形式で、とても楽しくウナギのことが勉強できます。
-