「モノ・コト・ヒト」とアーカイブズ資料、映像資料
セクションアウトライン
-
■概要本講義では,アーカイブズ資料(記録資料)や映像資料を手掛かりに博物館の「モノ・コト・ヒト」の関係性を考えます.本講義で扱うトピックはスライド2枚目の通りです.まずはじめに,1.ものへのさまざまな研究アプローチを紹介します.特に人類学の先行研究をひきつつ,ものとひとの関係を考えてみます.続いて,2.博物館における「モノ・コト・ヒト」について,標本,研究者,記録資料を取り上げながら説明します.最後に,3.「モノ・コト・ヒト」の各情報の発信方法について検討します.
-



ここに一つのモノがあります.(本当は実物をお見せしたいのですが.3枚のスライドは全て同じものを写しています.)
一体なんでしょうか?
よくわからないので観察してみます.
「どうやら木製で…長さ40㎝位...3本の足のようなものがついていて高さ10㎝位...紐もついている...人の手が加わった人工物だろう...」
「脚のように見えたのは,枝を活かしたものか...鑿で削ったような痕もある...表面を見ると焦がしてある...焦げで模様付けしている?...道具?」
というようなことは,推測できます.
-
何かしらの道具である可能性が高いです.でも,まだ分からないので,どのように作られたのかを想像してみます.
「鑿のようなもので木を削ったものである.幹についた枝を活かして脚のように作ってある.」
このような制作・技術情報は,モノにまつわる「コト」情報の一つで,モノ自体から抽出できる「コト」情報だと言えます.
しかしながら,モノ自体から抽出することが難しい/抽出できないコト情報もたくさんあります.
Q1.どのように使うのか,は物を観察すればヒントが得られるかもしれませんが,
Q2.誰がどのように入手したのか,については物を観察しても全く分かりません.
博物館では,モノにまつわるコト(コンテクスト)情報の存在を意識することが重要です.
-
ここからは,ものへの様々なアプローチを見ていきます.
一つ目は物質文化研究(MaterialCulture)というアプローチです.
歴史考古学や民俗学,技術史などが関係する研究分野で,日本では物質文化研究会なども組織されています.
物質文化研究における「もの」の定義,つまり物質文化研究が扱う「もの」は,「人の手が加えられた人工物」です.自然物については「もの」とみなしません.
ここでは,ものの制作過程や制作技術,道具としての意味などが主な研究対象とされています.
しかし,「人間にとってものとはそもそも何か」を問うようなアプローチはあまり見かけませんし,そもそも「人間の手助けをする道具としての<もの>」という前提からスタートしているので,いわゆる「道具的モノ観」に寄っている,とみなされることもあります.
-
つづいて,ものへのアプローチとして「モノ・感覚価値研究会(→身心変容技法研究会)」のアプローチを紹介します.
この研究会は,宗教学者・哲学者の鎌田東二氏(元京大こころの未来研究センター教授,神職・神道ソングライター)が代表,芸術家をふくめたメンバーから構成されており,「もの研究」のアプローチとして近年特異な活動でした.
日本人のモノ認識や感覚価値(カワイイ(→KAWAIIは国際化しましたね),カッコイイ,コワイなどの価値etc)を分析し,また表現も行いましたが,「モノにも命・霊性が宿る」という観念をもとに研究や活動を行いました.
研究会ウェブページの「モノ学・感覚価値研究会」とは?(http://mono-gaku.la.coocan.jp/)の中に,次のような一文があります.
「モノ」が単なる「物」ではなく、ある霊性を帯びた「いのち」を持った存在であるという「モノ」の見方の中に、「モノ」と人間、自然と人間、道具や文明と人間との新しい関係の構築可能性があると考えます。
活動自体は,かなり…アバンギャルドです.
(参考youtube:研究会代表の鎌田が京大植物園の廃園騒動を背景にして,同植物園祭りでライブ「森のヌシ神に捧ぐ」を行っています.)人間がものを道具のように使うのではなく,ものの方から人間に働きかけるということになります.
ここでは,道具的モノ観から脱却し,人間中心の文明認識を捉えなおす,という主張にひとまず注目してください.
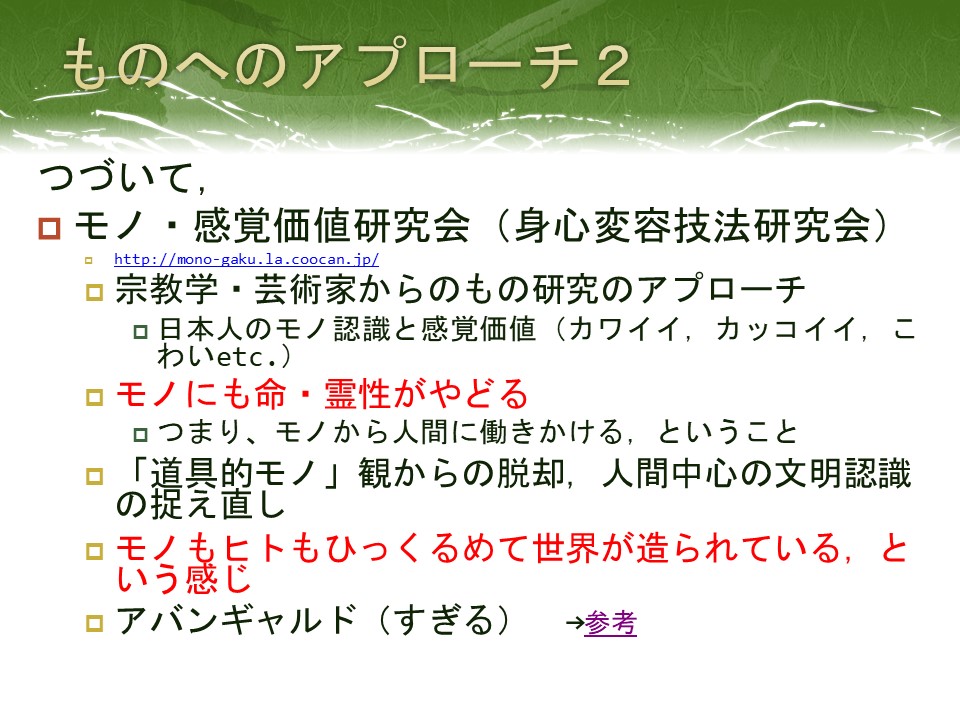
-
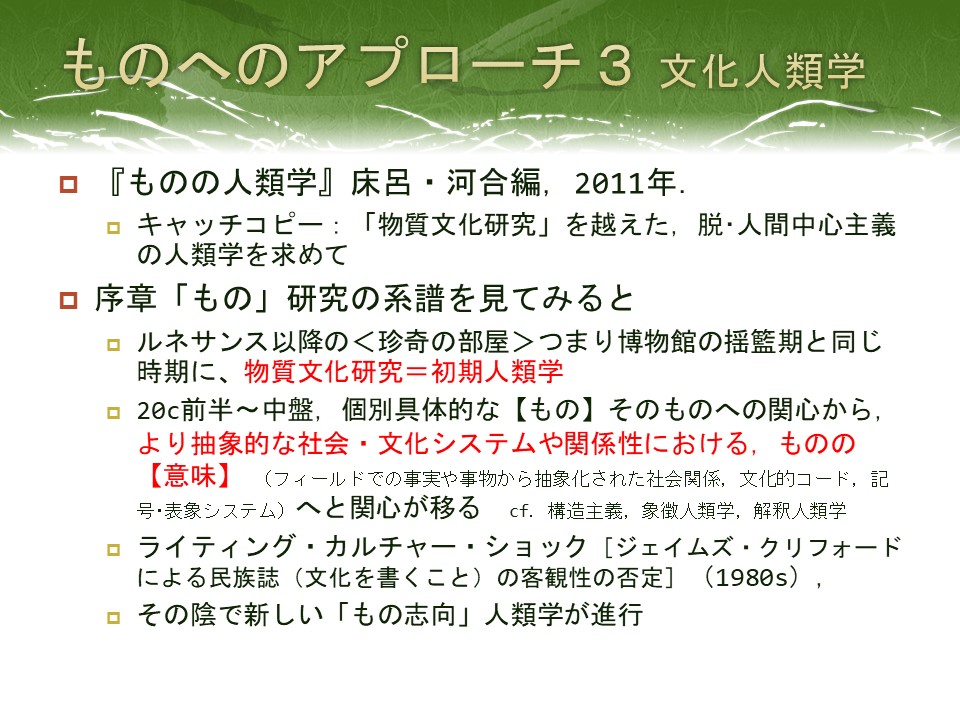
次に注目するのが,文化人類学者による「もの」へのアプローチです.
文化人類学者の床呂らは,本の帯に「「物質文化研究」を越えた,脱・人間中心主義の人類学を求めて」というキャッチコピーを掲げた『ものの人類学』を2011年に出版しています.
コピー通り新しい「もの」研究を希求した書籍ですが,その序章には,人類学における「もの」研究の系譜が要点を押さえてまとめられています.
概観すると,ルネサンス以降に生まれた<珍奇の部屋>(あるいは驚異の部屋),つまり博物館の揺籃期とみなしうる時期に,初期人類学は物質文化研究とほぼイコールなものとして生まれた,と述べられています.学術的・経済的な好奇心に突き動かされて,未開の地に足を延ばし,珍しいもの(異文化)収集し,知ることが人類学(あるいは博物館も)の出発点であった,ということになります.
その後,20世紀の前半から中盤にかけて,個別具体的な「もの」そのものへの関心から,より抽象的な社会・文化システム,あるいは関係性における<ものの「意味」>へと関心が移ってきたとされます.(例えば,ある共同体のフィールド調査において,共同体構成員の誰かが誰かに贈り物をしたのを見たとき,(極端に言えば)贈ったモノの物質的特徴ではなく,社会関係や社会における意味に注目する.)構造主義や,象徴人類学などに代表される「もの」の捉え方・扱い方です.物質的な「もの」そのものには注目されない時期といっても良いかもしれません.
こうして人類学が科学としての力を持ちつつあった時に起きた出来事が1980年代のライティング・カルチャー・ショックでした.J.クリフォードは『文化を書く』 (Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography)の中で,民俗誌を書くことの客観主義を否定し,創作的な作品であると位置づけ,人類学の拠り所を大きく揺るがしました.
その大きな混乱の陰に,新しい「もの志向」人類学が進行してきた,と床呂らはまとめています.

